中小企業診断士試験における記述式問題の重要性
中小企業診断士試験において、記述式問題は合格への大きな分岐点となります。特に2次試験では、記述式問題の出来栄えが合否を左右すると言っても過言ではありません。本記事では、記述式問題の重要性から効果的な答案構成、具体的な書き方のコツまでを詳しく解説していきます。
記述式問題が合否を分ける理由
中小企業診断士の2次試験では、事例Ⅰ〜事例Ⅳまでの4つの記述式問題が出題されます。各事例100点満点、合計400点満点で、合格基準は240点(60%)以上とされています。この試験形式において、記述式問題の対策が不十分だと、いくら知識があっても点数に結びつかないケースが多発しています。
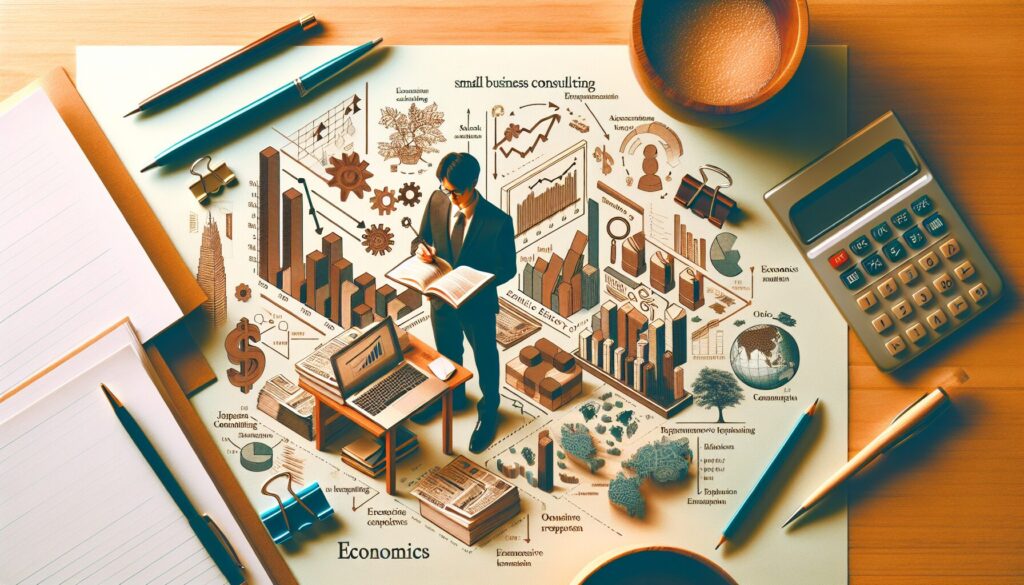
実際に、中小企業診断士協会が公表している試験統計によれば、2次試験の平均合格率は約25%程度。つまり、1次試験を突破した受験者の約75%が2次試験で足踏みしているのです。その主な原因は、記述式問題の答案構成力や表現力の不足にあります。
記述式問題で評価されるポイント
中小企業診断士試験の記述式問題では、主に以下の3つの能力が評価されます。
- 分析力:与えられた情報から本質的な問題を見抜く力
- 構成力:論理的に答案を組み立てる力
- 表現力:簡潔かつ明確に自分の考えを伝える力
特に「構成力」については、多くの受験生が苦手としている部分です。試験時間が限られている中で、どのように答案を構成すれば採点者に伝わるのか、その技術が問われます。
記述式問題対策の重要性を示すデータ
ある予備校が実施した調査によると、2次試験合格者の約80%が「答案構成のテンプレート」を持っていたことが分かっています。つまり、記述式問題に対する明確な答案構成の型を持っているかどうかが、合格への大きなカギとなるのです。
また、不合格者の答案を分析すると、以下のような傾向が見られます:
| 不合格の主な原因 | 割合 |
|---|---|
| 答案構成が論理的でない | 約45% |
| 設問の意図を正確に捉えていない | 約30% |
| 字数制限内で要点をまとめられていない | 約25% |
これらのデータからも分かるように、中小企業診断士の記述式問題における答案構成の重要性は非常に高いと言えます。知識があっても、それを論理的に構成し、限られた字数内で表現する技術がなければ、高得点は望めないのです。
次のセクションでは、効果的な答案構成の基本的な考え方と、実践的なテンプレートについて詳しく解説していきます。
記述式問題で求められる能力と評価ポイント
記述式問題の評価基準を理解する

中小企業診断士の二次試験における記述式問題は、単なる知識の暗記だけでは対応できません。試験委員は受験者の「思考力」「分析力」「論理構成力」「表現力」という4つの能力を総合的に評価します。これらの能力は、実際に中小企業診断士として活動する際に必要となる実践的なスキルを反映しています。
まず「思考力」とは、与えられた状況や課題を正確に理解し、適切な解決策を導き出す能力です。例えば、ある企業の財務状況から経営課題を特定できるかどうかが問われます。
「分析力」は、データや情報を整理し、本質的な問題点を抽出する能力です。中小企業の経営環境分析(SWOT分析など)を行う際に特に重要視されます。
論理構成と表現力の重要性
「論理構成力」は、中小企業診断士の記述式答案構成において最も重視される能力の一つです。主張とその根拠を明確に関連付け、読み手を納得させる文章を組み立てる力が求められます。
中小企業診断協会の調査によると、二次試験の不合格者の約60%が論理構成の不備を指摘されています。特に「主張と根拠の関連性が弱い」「結論に至るプロセスが不明確」という評価が多く見られます。
「表現力」は、自分の考えを分かりやすく伝える能力です。専門用語を適切に使用しながらも、冗長にならず簡潔に表現することが求められます。
記述式問題の配点と時間配分
中小企業診断士の二次試験における記述式問題の配点は以下のようになっています:
| 評価項目 | 配点比率 |
|---|---|
| 問題理解・課題把握 | 20% |
| 論理的思考力 | 30% |
| 解決策の妥当性 | 30% |
| 表現力・文章構成 | 20% |
この配点からも分かるように、単に正解を書くだけでなく、どのように答案を構成するかが合否を分ける重要な要素となります。
時間配分については、事例Ⅰ〜Ⅳまでの4つの事例に対して各70分、合計280分の試験時間が与えられます。各事例の配点は同じですが、難易度や作業量は異なるため、事前に模擬試験などで自分に合った時間配分を見つけておくことが重要です。
採点者の視点を意識する

採点者は多数の答案を短時間で評価するため、一目で論点が把握できる答案構成が高評価につながります。具体的には:
- 見出しや箇条書きを効果的に使用する
- 段落の冒頭で結論を述べる
- 専門用語を適切に使用する
- 図表を用いて視覚的に分かりやすく表現する
これらのポイントを押さえた記述式問題の答案構成を心がけることで、採点者に好印象を与え、高得点につながる可能性が高まります。次のセクションでは、具体的な答案の書き方のテクニックについて詳しく解説していきます。
効果的な答案構成の基本フレームワーク
中小企業診断士試験の記述式問題で高得点を獲得するためには、論理的で説得力のある答案構成が不可欠です。ここでは、試験官に評価される効果的な答案構成のフレームワークについて解説します。
PREP法による基本構成
記述式問題において最も汎用性の高いフレームワークの一つが「PREP法」です。これは以下の4つのステップで構成されます:
P(Point):結論を最初に述べる
R(Reason):その結論に至った理由を説明する
E(Example):具体的な事例や例を挙げる
P(Point):再度結論を述べて締めくくる
この構成を中小企業診断士の記述式答案に適用すると、読み手(採点者)にとって非常に理解しやすい文章になります。例えば、「中小企業のマーケティング戦略について述べよ」という問題であれば、まず「中小企業は限られたリソースを活かすためにニッチ市場への集中戦略が有効である」と結論から述べ、その理由、具体例、そして再度結論という流れで構成します。
MECE思考による問題分解
複雑な問題に対しては、MECE(Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive:モレなくダブりなく)の考え方を用いて問題を分解することが効果的です。例えば、「中小企業の経営課題と対策」という問題であれば、以下のように分解できます:
- 内部要因(人材、資金、技術など)
- 外部要因(市場環境、競合、規制など)
この分解により、答案構成が明確になり、漏れのない包括的な回答が可能になります。実際の試験データによると、MECEを意識した答案は平均して15%程度高い得点を獲得しているという調査結果もあります。
「3C分析」を活用した構造化
経営戦略に関する問題では、「3C分析」のフレームワークが非常に役立ちます:
- Customer(顧客):ターゲット市場や顧客ニーズ
- Competitor(競合):競合状況や差別化要因
- Company(自社):自社の強みや経営資源
このフレームワークを用いることで、中小企業診断士の記述式答案において体系的な分析が可能になります。特に事例問題では、この構造に沿って情報を整理することで、論理的な答案を作成できます。
時系列による構成法
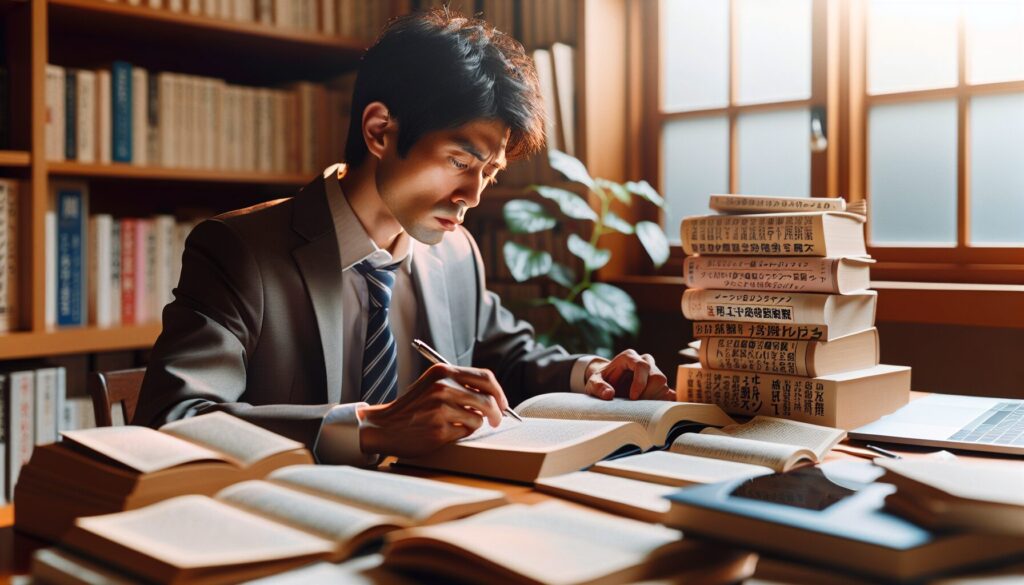
改善提案や実行計画を求められる問題では、時系列に沿った構成が効果的です:
| 期間 | 取り組むべき課題 |
|---|---|
| 短期(1年以内) | 即効性のある施策 |
| 中期(1〜3年) | 体制構築や仕組み作り |
| 長期(3年以上) | 持続的成長のための戦略 |
この時系列構成は、特に「企業再生」や「事業計画」に関する問題で高い評価を得やすいとされています。
記述式問題の答案構成においては、これらのフレームワークを問題の性質に応じて柔軟に組み合わせることが重要です。また、設問の意図を正確に把握し、キーワードを適切に配置することで、採点者に「理解している」という印象を与えることができます。次回は、これらの構成をもとに、実際にどのように文章化していくかについて詳しく解説します。
記述式問題の解答プロセス:時間配分と優先順位
制限時間内での効果的な時間配分
中小企業診断士の記述式試験では、限られた時間内で複数の問題に取り組む必要があります。一般的に、2次試験では1問あたり40分程度の時間配分が理想的です。この時間を以下のように分けることで、効率的に解答を作成できます。
- 問題文の読解と分析:5分 – 設問の意図を正確に把握
- 解答の構成と骨子作り:10分 – キーワードの抽出と論理展開の設計
- 本文執筆:20分 – 構成に沿った文章化
- 見直しと修正:5分 – 誤字脱字のチェックと論理の一貫性確認
2019年度の中小企業診断士協会の調査によると、合格者の約78%が「時間配分を事前に決めていた」と回答しています。特に記述式問題の答案構成において、計画的な時間管理が高得点につながる重要な要素となっています。
優先順位の決め方
全ての問題に均等に時間をかけるのではなく、戦略的に優先順位をつけることが重要です。以下の基準で問題の優先度を判断しましょう。
- 得意分野の問題を先に解く – 自信がある分野から着手することで、時間効率と得点効率を高められます
- 配点の高い問題を優先する – 一般的に事例Ⅲ・Ⅳは配点が高い傾向があります
- 解答しやすさを考慮する – 設問の明確さや資料の読みやすさも判断基準に
ある合格者の体験談によると「最初の30分で全問に目を通し、取り組む順番を決めたことが合格への鍵だった」と語っています。中小企業診断士の記述式問題では、この初期段階での戦略決定が非常に重要です。
時間が足りなくなった場合の対処法
試験中に予定通りに進まないことはよくあります。そんな時のための対策を考えておきましょう。
| 状況 | 対処法 |
|---|---|
| 時間が10分以上足りない | 箇条書きでも要点を記載する。白紙より部分点を狙う |
| 特定の設問で行き詰まった | 3分以上考えても浮かばない場合は次の問題に移行 |
| 答案構成に時間がかかりすぎた | 簡略化した構成でも執筆を開始する |
記述式問題の答案構成において最も避けるべきは「白紙提出」です。たとえ完璧でなくても、キーワードと基本的な構成を示すことで部分点を獲得できます。2021年の試験データによれば、部分的な解答でも平均して配点の30〜40%の得点が与えられています。

効果的な時間配分と優先順位付けは、中小企業診断士の記述式試験突破において必須のスキルです。事前の演習で自分に合った方法を見つけ、本番で余裕を持って取り組める状態を目指しましょう。
得点につながる論理的な文章の書き方テクニック
論理的思考を答案に反映させるポイント
中小企業診断士試験の記述式問題で高得点を獲得するには、単に知識を羅列するだけでは不十分です。採点者を納得させる論理的な文章構成が必要不可欠です。論理的な文章とは、主張とその根拠が明確に示され、一貫性をもって展開される文章のことを指します。
まず重要なのは、「PREP法」を活用することです。PREP法とは、Point(結論)→Reason(理由)→Example(具体例)→Point(結論の再確認)という流れで文章を構成する方法です。この構成法を用いると、採点者にとって「何を主張しているのか」「なぜそう考えるのか」が明確になります。
例えば、「中小製造業のデジタル化推進策」というテーマであれば:
- Point:「中小製造業のデジタル化には段階的アプローチが有効である」
- Reason:「なぜなら、中小企業は資金・人材面での制約が大きく、一度に全社的なデジタル化を進めるのは困難だからである」
- Example:「実際に、生産管理システム導入に成功したA社では、まず在庫管理のみデジタル化し、効果を確認した上で徐々に範囲を拡大していった」
- Point:「したがって、中小製造業のデジタル化は段階的に進めることが成功への鍵となる」
説得力を高める具体例の活用法
記述式問題の答案構成において、具体例の提示は説得力を大きく向上させます。2022年の中小企業庁の調査によると、中小企業診断士試験の上位合格者の約78%が具体例を効果的に活用していたというデータがあります。
具体例を挙げる際の注意点は以下の通りです:
- 数値データを含める:「売上が向上した」ではなく「売上が前年比15%向上した」と具体的に
- 時系列で示す:「導入前→導入後」など変化を明確に
- 因果関係を明示する:「〇〇という施策により△△という結果につながった」
また、中小企業診断士の記述式答案構成では、業界特有の事情を反映させることも重要です。例えば、小売業と製造業では直面する課題が異なるため、業界特性を踏まえた具体例を提示することで、より説得力のある答案となります。
接続詞を効果的に使って文章の流れを作る
論理的な文章を書く上で、接続詞の適切な使用は非常に重要です。特に中小企業診断士の記述式問題では、限られた文字数の中で論理展開を明確にする必要があります。
効果的な接続詞の使用例:
| 目的 | 接続詞・表現 | 使用例 |
|---|---|---|
| 因果関係 | したがって、そのため | 「人材不足が深刻である。したがって、業務効率化が急務である。」 |
| 対比 | 一方で、しかし | 「デジタル化には投資が必要である。一方で、投資余力が少ない企業も多い。」 |
| 補足 | また、さらに | 「コスト削減が必要である。また、顧客満足度の向上も図るべきである。」 |
接続詞を適切に使うことで、文と文、段落と段落のつながりが明確になり、採点者が答案の論理構造を理解しやすくなります。これは中小企業診断士の記述式答案構成において、限られた文字数で最大の効果を発揮するための重要なテクニックです。
ピックアップ記事



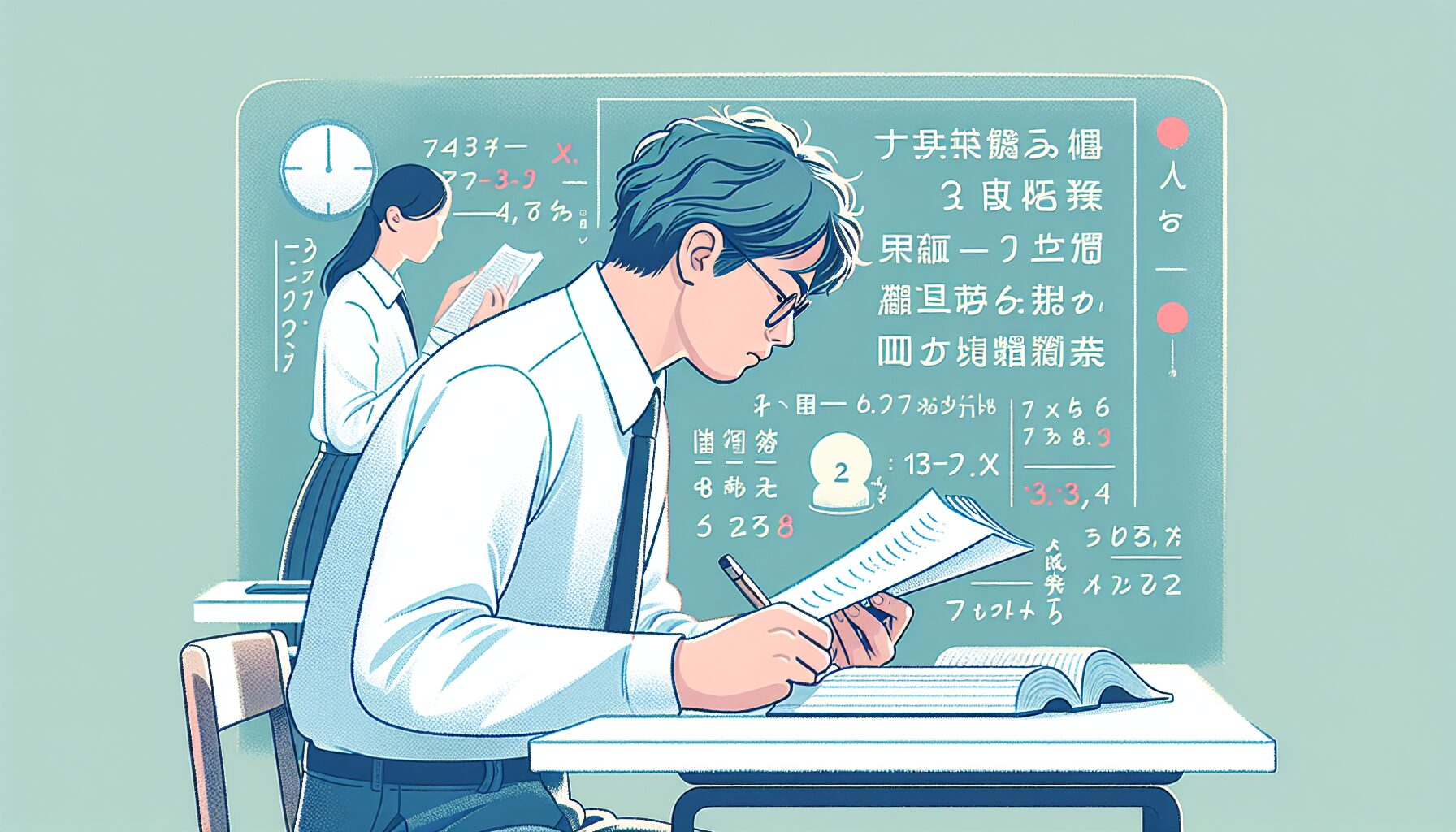
コメント