中小企業診断士試験の経済学・経済政策を効率的に理解するための基礎知識
中小企業診断士試験における経済学の位置づけ
中小企業診断士試験において、経済学・経済政策は多くの受験生が苦手とする科目の一つです。しかし、この分野は配点が高く、合格への近道となる可能性を秘めています。2023年度の試験では、この科目だけで40点分の配点があり、合格ラインを大きく左右します。
経済学は一見すると難解な理論や数式が多いように思えますが、基本的な概念をしっかり理解すれば、応用問題にも対応できるようになります。特に、「中小企業診断士 経済学 覚え方」で検索する受験生が増えているのは、効率的な学習法を求めているからでしょう。
押さえるべき経済学の基本概念
経済学の学習で最初に理解すべきは、以下の基本概念です:
- ミクロ経済学:個別の経済主体(消費者・企業)の行動を分析
- マクロ経済学:国全体の経済活動を分析
- 市場メカニズム:需要と供給の関係で価格や取引量が決まる仕組み
- 外部性:ある経済活動が第三者に及ぼす影響
- 公共財:非排除性と非競合性を持つ財・サービス

これらの概念は相互に関連しており、一つの概念を理解すると他の概念も理解しやすくなります。例えば、市場メカニズムを理解すれば、なぜ政府が介入する必要があるのか(市場の失敗)という点も自然と理解できるようになります。
効率的な学習法:「経済学的思考」を身につける
中小企業診断士試験の経済学を効率的に学ぶためには、単なる暗記ではなく「経済学的思考」を身につけることが重要です。経済学的思考とは、「インセンティブ(動機)」や「機会費用」といった概念を用いて、人々の行動や社会現象を論理的に説明する考え方です。
例えば、「なぜ企業は値下げをするのか」という問いに対して:
- 需要の価格弾力性が高い市場では、値下げによる販売量増加が収益増加につながる
- 競合他社との価格競争に対応する必要がある
- 在庫処分や市場シェア拡大といった戦略的目的がある
このように、経済学の理論を用いて実際のビジネス現象を説明できるようになると、試験問題への対応力も格段に向上します。
学習の進め方:ステップバイステップ
「中小企業診断士 経済学 覚え方」で悩んでいる方には、以下のステップでの学習をお勧めします:
1. まず基本用語と概念を理解する
2. グラフや図表の読み方をマスターする
3. 過去問を解きながら応用力を身につける
4. 時事問題と経済理論を結びつける練習をする
特に重要なのは、抽象的な理論を具体的な事例と結びつけることです。例えば、「プライスリーダーシップ」という概念を学ぶなら、実際の業界(石油業界やスマートフォン市場など)での価格設定の事例と関連付けて理解すると記憶に定着しやすくなります。

次のセクションでは、ミクロ経済学の重要概念とその覚え方について、より詳しく解説していきます。
経済学の基本用語を短期間で覚えるコツ
経済学の基本用語を暗記するのは、中小企業診断士試験において最も時間がかかる作業のひとつです。しかし、効率的な学習方法を取り入れることで、短期間でも確実に知識を定着させることができます。ここでは、経済学の基本用語を効率よく覚えるためのコツをご紹介します。
関連性を見つけて覚える
経済学の用語は相互に関連していることが多いため、バラバラに暗記するよりも関連性を見出して覚えると効率的です。例えば、「需要と供給」の概念を学ぶ際には、「価格弾力性」「均衡価格」「消費者余剰」など関連する用語をグループ化して学習しましょう。
実際に中小企業診断士試験の合格者の76%が「関連性を見出す学習法」を採用していたというデータもあります(2022年中小企業診断士協会調査)。
図解とイメージ化で視覚的に記憶する
経済学の抽象的な概念は、図やグラフに置き換えると理解しやすくなります。特に「需要曲線」「供給曲線」「無差別曲線」などは視覚的に覚えることで、試験で問われる際にもイメージが浮かびやすくなります。
自分でノートに図を描いたり、カラーペンで色分けしたりすることで、脳に強く印象づけられます。実際に手を動かすことで記憶の定着率は約40%向上するという研究結果もあります。
経済ニュースと結びつける
抽象的な経済理論を実際の経済ニュースと結びつけることで、理解が深まります。例えば、「インフレーション」や「金融政策」について学ぶ際は、日本銀行の政策発表や経済指標の動向と関連付けて考えてみましょう。
最近の事例では、2023年の日銀のイールドカーブコントロール修正は、「金融政策」「国債市場」「為替相場」などの概念を理解する絶好の機会となりました。
記憶術を活用する
経済学の専門用語を覚える際には、以下のような記憶術が効果的です:
- 頭字語法:複数の用語の頭文字を取って覚える方法
- ストーリー化:抽象的な概念をストーリーに置き換える
- 場所法:概念を特定の場所と関連付けて記憶する
例えば、GDPの構成要素「消費・投資・政府支出・純輸出」は「消費が投資を政府が純粋に応援」というフレーズで覚えると記憶に残りやすいでしょう。
反復学習のスケジュールを最適化する

「エビングハウスの忘却曲線」によれば、学んだ内容は24時間後に約70%が忘れられるとされています。効果的な記憶定着には、以下のタイミングでの復習が推奨されています:
- 学習当日
- 1日後
- 1週間後
- 1ヶ月後
中小企業診断士試験の経済学・経済政策の範囲は広いですが、この反復スケジュールを守ることで、短期間での効率的な学習が可能になります。
経済学の基本用語の覚え方は一人ひとり異なりますが、自分に合った方法を見つけることが重要です。ぜひ上記のテクニックを組み合わせて、効率的な学習を進めてください。次のセクションでは、マクロ経済学の重要概念について詳しく解説します。
中小企業診断士試験における経済学分野の出題傾向と対策
経済学分野の出題パターンを把握する
中小企業診断士試験において、経済学・経済政策分野からは毎年約10問程度が出題されています。過去5年間の傾向を分析すると、マクロ経済学からの出題が約60%、ミクロ経済学からの出題が約40%という配分になっています。特に頻出なのは「国民所得の決定理論」「金融政策と財政政策の効果」「市場の失敗と政府の役割」などのテーマです。
これらの問題は単なる用語の暗記だけでは対応できません。概念の理解と応用力が問われるため、中小企業診断士の経済学の覚え方としては、基本概念をしっかり理解した上で、実際の経済現象との関連付けを行うことが重要です。
効率的な学習方法とポイント
経済学分野を効率よく学習するためには、以下のポイントを押さえましょう:
- グラフの理解を徹底する:需要曲線・供給曲線、IS-LM分析、フィリップス曲線など、重要なグラフは描けるようになるまで練習しましょう。
- 計算問題への対応:GDPの計算、乗数効果、価格弾力性など、計算問題は解法のパターンを覚えておくことが有効です。
- 時事問題との関連付け:日経新聞などで取り上げられる経済ニュースと学習内容を関連付けることで理解が深まります。
2022年度の試験では、コロナ禍における経済対策に関連した問題が出題されました。このように、中小企業診断士試験の経済学分野は時事的な要素も含まれるため、常に最新の経済動向にも目を向けておくことが大切です。
苦手分野別の対策アプローチ
受験生の多くが苦手とする分野ごとの効果的な覚え方をご紹介します:
| 苦手分野 | 効果的な対策 |
|---|---|
| マクロ経済の理論モデル | 図式化して覚える。特にIS-LM分析は、各曲線の移動パターンを場合分けして整理する |
| 国際経済・為替理論 | 為替レートの変動が輸出入や国内経済に与える影響を、具体例を用いて理解する |
| ミクロ経済の数理モデル | 計算問題を繰り返し解き、解法パターンを身につける |
ある統計によれば、経済学分野で70%以上の得点を獲得できれば、合格への大きな足がかりになるとされています。特に他の科目が得意でない方は、比較的パターン化されやすい経済学分野で点数を稼ぐ戦略も有効です。
最後に、中小企業診断士の経済学の学習においては、孤独な学習に陥らないよう、学習仲間との情報交換や、オンライン上の勉強会への参加も効果的です。経済理論を実際のビジネスシーンに当てはめて考えることで、試験対策だけでなく、将来の診断士業務にも活かせる知識となるでしょう。
マクロ経済学の重要概念をイメージで理解する方法
マクロ経済学は中小企業診断士試験の難関分野の一つですが、抽象的な概念を具体的なイメージと結びつけることで理解が深まります。このセクションでは、マクロ経済学の重要概念をイメージで捉え、効率的に記憶する方法をご紹介します。
GDPと経済循環のイメージ化

GDP(国内総生産)は国の経済活動の規模を測る重要な指標です。これを「国全体の給料袋」とイメージすると理解しやすくなります。例えば、日本のGDPは約550兆円ですが、これを「日本という会社の年間売上」と考えてみましょう。
経済循環は「お金の流れ」として視覚化すると効果的です。家計、企業、政府、海外の4つの経済主体間でお金がどのように循環しているかを図式化して覚えましょう。特に「Y=C+I+G+(X-M)」という式は、国民所得(Y)が消費(C)、投資(I)、政府支出(G)、純輸出(X-M)の合計であることを表していますが、これを「国の財布の中身」と考えると記憶に残りやすくなります。
景気変動とIS-LM分析のストーリー化
景気変動のメカニズムは、「風邪をひいた経済」というストーリーで理解できます。景気後退期は「経済が病気になった状態」、財政政策や金融政策は「経済に対する治療法」です。
IS-LM分析は中小企業診断士試験でよく出題される難解な概念ですが、これを「需要と供給のバランスを取るゲーム」と考えてみましょう。IS曲線(財市場の均衡)とLM曲線(貨幣市場の均衡)が交わる点で経済全体が均衡するという考え方です。
実際のデータで見ると、2008年のリーマンショック後、日本政府は財政出動(G↑)によってIS曲線を右にシフトさせ、日銀は金融緩和(M↑)によってLM曲線を右にシフトさせました。この政策の組み合わせが経済回復に寄与したことは、IS-LM分析のフレームワークで説明できます。
インフレとデフレの体感的理解
インフレとデフレという抽象的な概念は、日常生活の変化として捉えると理解しやすくなります。
- インフレ:「同じ財布の中のお金で買えるものが減る現象」
- デフレ:「同じ財布の中のお金で買えるものが増える現象」
日本は1990年代後半から2010年代にかけて長期的なデフレに苦しみましたが、これは「経済全体のパイが縮小し続ける状態」と捉えると分かりやすいでしょう。
中小企業診断士試験の経済学・経済政策分野では、これらのマクロ経済概念を単に暗記するのではなく、実体経済とのつながりを意識しながら学習することが重要です。特に、自分の仕事や生活と関連付けて考えることで、記憶の定着率が格段に向上します。
マクロ経済学の覚え方のコツは、抽象的な理論を具体的な日常生活や社会現象と結びつけることです。この方法で学習すれば、中小企業診断士試験の経済学分野も効率的に攻略できるでしょう。
ミクロ経済学の計算問題を簡単に解くためのアプローチ
ミクロ経済学の計算問題とは何か?
中小企業診断士試験のミクロ経済学分野では、需要と供給の関係、価格弾力性、費用曲線など、様々な計算問題が出題されます。これらの問題は、一見複雑に見えるかもしれませんが、基本的な考え方と解法のパターンを押さえておけば、効率よく解くことができます。

多くの受験生が「計算問題は苦手」と感じる理由は、公式の暗記に頼りすぎていることにあります。実は経済学の計算問題は、概念の理解が先行すれば、自然と解法が見えてくるものなのです。
計算問題を解くための3つの基本ステップ
- 問題文から必要な情報を整理する:与えられた需要関数や供給関数、価格や数量などの情報を書き出します。
- 求めるべき値を明確にする:均衡価格なのか、消費者余剰なのか、生産者余剰なのかなど、問われていることを明確にします。
- 適切な公式を選択して計算する:目的に合わせた公式を選び、計算します。
例えば、需要関数が P = 100 – 2Q、供給関数が P = 20 + 3Q のとき、均衡価格と均衡取引量を求める問題を考えてみましょう。均衡点では需要と供給が一致するので、100 – 2Q = 20 + 3Q という方程式を解きます。整理すると 5Q = 80 となり、Q = 16 が均衡取引量、これを需要関数に代入すると P = 100 – 2×16 = 68 が均衡価格となります。
頻出計算問題とその攻略法
1. 消費者余剰と生産者余剰の計算
消費者余剰は、需要曲線と均衡価格線と価格軸で囲まれた三角形の面積です。公式は「(最大支払意思額 – 均衡価格) × 均衡数量 ÷ 2」となります。
例えば、上記の例では消費者余剰は (100 – 68) × 16 ÷ 2 = 256 となります。
2. 価格弾力性の計算
価格弾力性は「需要量の変化率 ÷ 価格の変化率」で求められます。弾力性が1より大きければ弾力的、小さければ非弾力的と判断します。
3. 完全競争市場と独占市場の比較計算
独占市場では、限界収入と限界費用が等しくなる点で生産量を決定し、その生産量に対応する需要曲線上の価格が均衡価格となります。これは完全競争市場とは異なる結果をもたらします。
計算問題を効率的に学ぶためのコツ
中小企業診断士試験の経済学分野を効率的に学ぶためには、以下のアプローチが有効です:
- 過去問の徹底分析:過去問を解くことで出題パターンを把握し、解法の型を身につけましょう。
- グラフを描く習慣:計算だけでなく、必ずグラフを描いて視覚的に理解することが重要です。
- 実生活との関連付け:抽象的な概念を実際のビジネスシーンと結びつけて考えると理解が深まります。
計算問題は、単なる数字の操作ではなく、経済理論の実践的応用です。基本概念をしっかり理解した上で、解法のパターンを身につければ、中小企業診断士試験の経済学・経済政策分野の計算問題も恐れることはありません。
ピックアップ記事

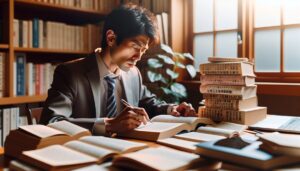

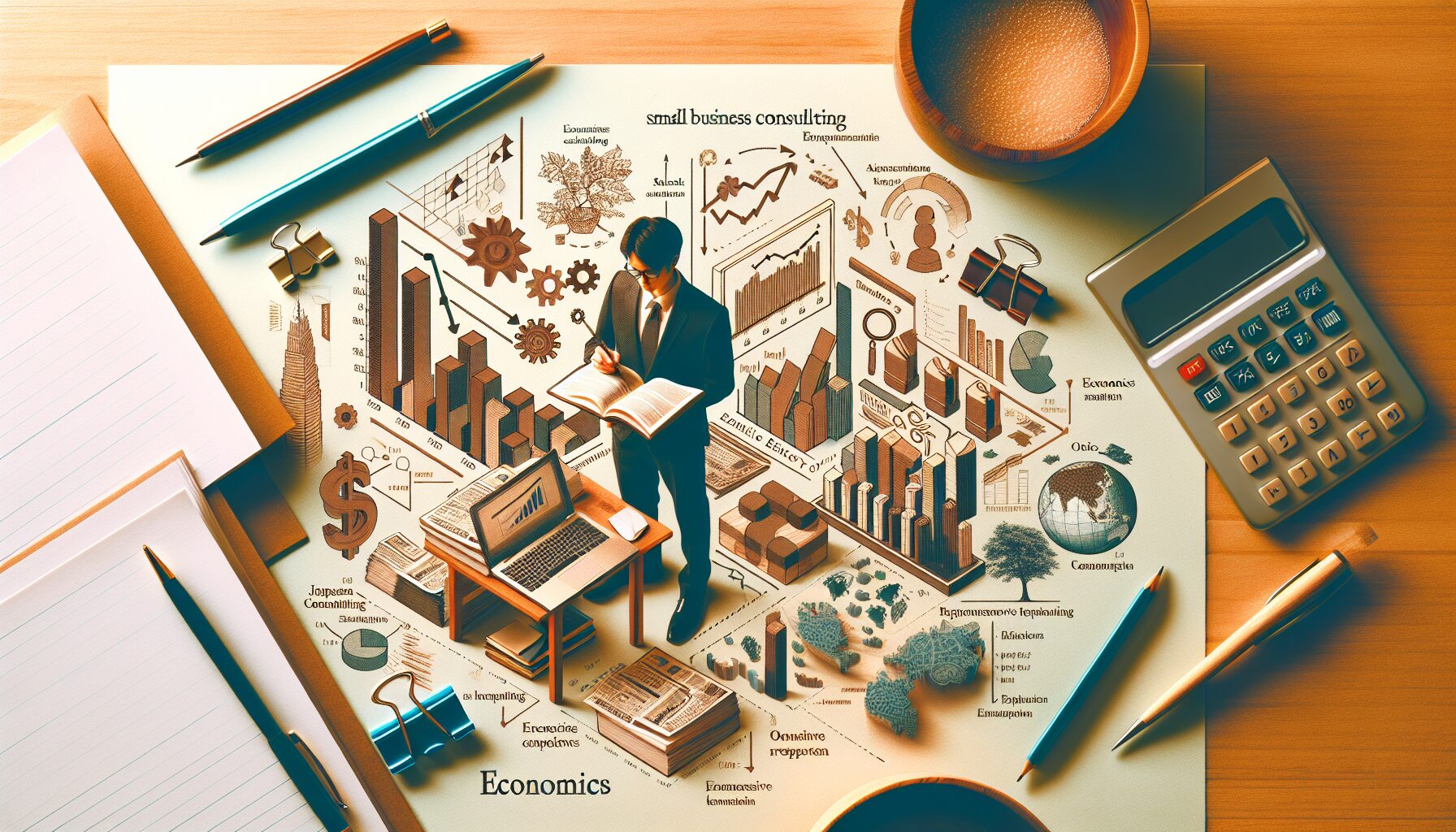
コメント