中小企業診断士試験における事例問題の基本構造と特徴
中小企業診断士試験の2次試験において、事例Ⅰ〜Ⅳの問題は合否を分ける重要な関門です。これらの問題には独自の構造と特徴があり、解答作成にはそれを理解することが不可欠です。本記事では、効果的な解答テクニックを身につけるための基礎知識をご紹介します。
事例問題の基本構造を理解する
中小企業診断士の事例問題は、架空の企業に関する詳細な情報(財務諸表、経営状況、市場環境など)が提示され、それに基づいて具体的な経営課題の分析や解決策の提案を求められる形式となっています。各事例問題には以下の共通構造があります:
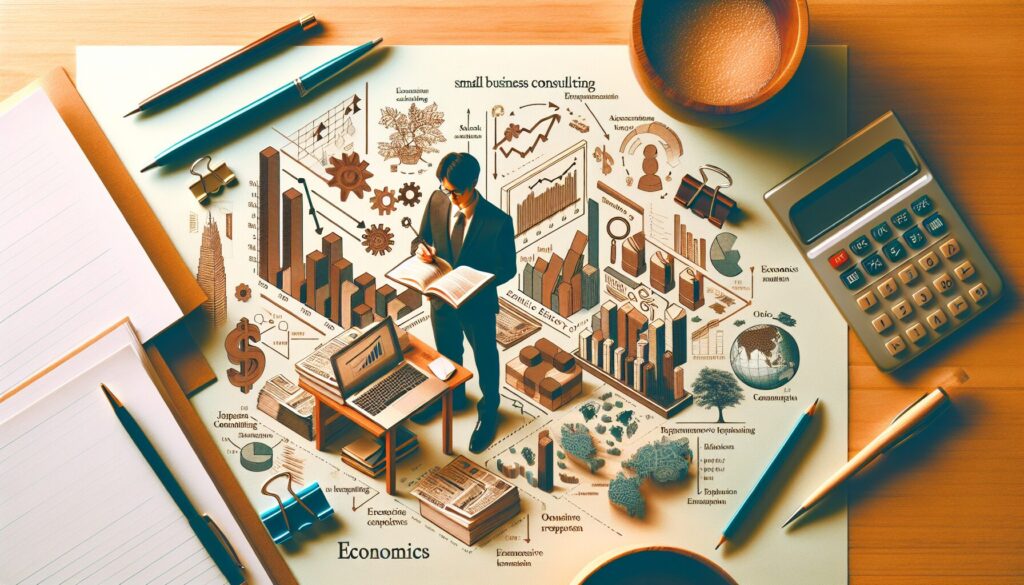
1. 設問文:何を回答すべきかの指示
2. 事例本文:企業情報や背景
3. 資料:財務データ、市場情報など
4. 解答用紙:字数制限付きの回答欄
特に重要なのは、事例Ⅰ〜Ⅳそれぞれが異なる能力を測定するように設計されている点です。事例Ⅰは経営戦略、事例Ⅱは組織・人事、事例Ⅲはマーケティング・流通、事例Ⅳは財務・会計という具合に、専門分野が異なります。
各事例問題の特徴と対策ポイント
| 事例 | 主な出題分野 | 求められる能力 |
|---|---|---|
| 事例Ⅰ | 経営戦略・経営計画 | SWOT分析や経営環境分析、中長期的視点での戦略立案 |
| 事例Ⅱ | 組織・人事 | 組織構造の分析、人材育成計画、モチベーション向上策 |
| 事例Ⅲ | マーケティング・流通 | 市場分析、販売戦略、プロモーション計画 |
| 事例Ⅳ | 財務・会計 | 財務諸表分析、資金計画、収益性改善策 |
過去の出題傾向を分析すると、事例問題では単なる知識の暗記ではなく、応用力と実践的な提案能力が求められていることがわかります。2022年度の試験では、コロナ禍を踏まえた事業再構築や、デジタル化への対応など、時事的な要素も多く含まれていました。
事例問題攻略の基本姿勢
中小企業診断士の事例問題解答テクニックで最も重要なのは、「診断士としての視点」を持つことです。これは、単に問題を解くのではなく、実際に企業を診断するコンサルタントとしての思考プロセスを示すことを意味します。
具体的には:
– 事実に基づいた客観的な分析
– 理論や手法を適切に活用した論理的な思考展開
– 実現可能で具体的な解決策の提示
初学者がよく陥る罠は、設問の意図を正確に把握せずに解答を作成してしまうことです。事例問題の解答テクニックを磨くには、まず設問の「求められていること」を正確に理解する訓練が必要です。
次のセクションでは、各事例問題の解答作成プロセスについて、より具体的に解説していきます。
事例Ⅰ:経営戦略の解答作成テクニックと得点のポイント
事例Ⅰの特徴と出題傾向を理解する
中小企業診断士の二次試験において、事例Ⅰは経営戦略に関する問題です。この科目では、企業の内部・外部環境分析から戦略立案までの一連のプロセスが問われます。多くの受験生が最初に取り組む科目であり、時間配分や解答の構成力が試されるポイントでもあります。
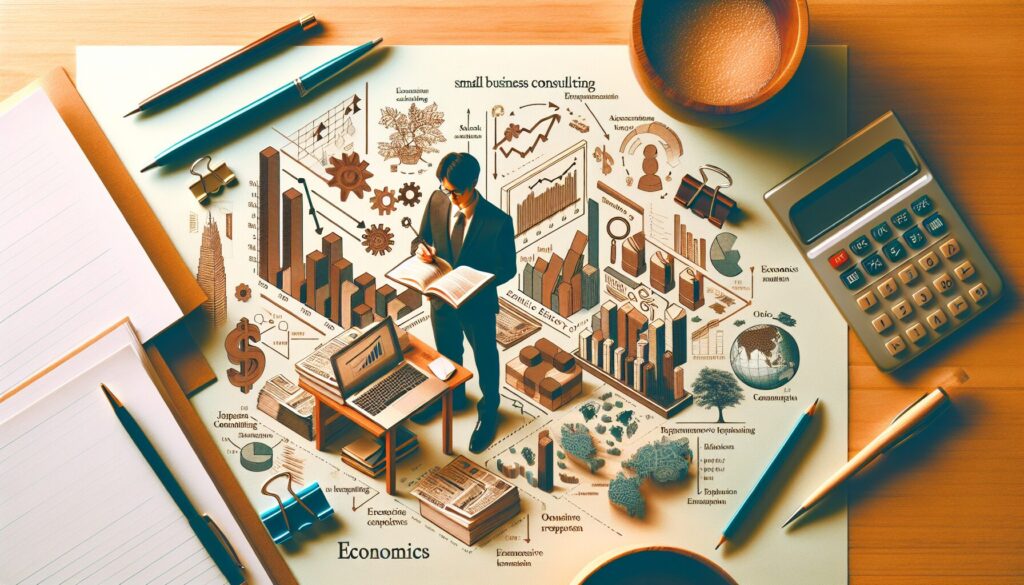
近年の出題傾向を見ると、SWOT分析、3C分析、PPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)などの経営分析フレームワークを活用した問題が頻出しています。2022年度の試験では、新規事業展開を検討する中小製造業に対して、市場分析と参入戦略の提案が求められました。
解答作成の基本的アプローチ
事例Ⅰの解答作成には、以下の3ステップアプローチが効果的です。
1. 問題文の徹底的な読み込みと情報整理
– 設問の要求を明確に把握する(何を問われているか)
– 事例文中の重要なデータや情報に線を引く
– 財務データや市場情報などの数値は必ずメモしておく
2. フレームワークの選択と適用
– 適切な分析フレームワークを選択(SWOT、3C、バリューチェーンなど)
– 事例企業の状況に合わせてカスタマイズする
– 分析結果を論理的に整理する
3. 解答の構成と記述
– 結論→理由→具体策の順で構成する
– 箇条書きや見出しを効果的に使用
– 具体的な数値や根拠を盛り込む
得点アップのための実践テクニック
中小企業診断士の事例問題解答テクニックとして、特に事例Ⅰでは以下の点に注意しましょう。
1. キーワードの活用:経営戦略特有の専門用語(コアコンピタンス、ブルーオーシャン戦略など)を適切に使用することで専門性をアピールできます。
2. 数値データの引用:「売上高が前年比15%減少している点から」など、具体的な数値を引用することで説得力が増します。
3. 図表の活用:時間に余裕があれば、簡単なマトリクス図やグラフを描くことも効果的です。ただし、過度に複雑な図表は避けましょう。
4. 中小企業の特性への言及:大企業とは異なる中小企業特有の課題(資金制約、人材不足など)に触れることで、診断士としての視点をアピールできます。

実際の試験では60分という限られた時間の中で、問題文の読解から解答作成まで行う必要があります。時間配分としては、読解・情報整理に15分、分析に15分、解答作成に30分を目安にするとバランスが良いでしょう。
事例Ⅰは配点が高い科目であり、ここでしっかり得点することが合格への近道となります。フレームワークの使い方を機械的に覚えるのではなく、実際の企業事例に適用する練習を重ねることで、応用力を身につけていきましょう。
事例Ⅱ:組織・人事の解答構築法と評価されるポイント
事例Ⅱの特徴と出題傾向
事例Ⅱは組織・人事分野の問題で、企業の人材育成、組織構造、労務管理など幅広いテーマが出題されます。近年の傾向を見ると、働き方改革、人材不足対策、モチベーション向上策などが頻出しています。この分野は理論と実践のバランスが重要で、単なる知識の羅列ではなく、具体的な企業状況に応じた提案が求められます。
解答構築の基本フレームワーク
事例Ⅱの解答作成では、以下の3ステップアプローチが効果的です:
- 現状分析:組織の問題点を「ヒト・モノ・カネ・情報」の視点から整理
- 課題抽出:問題の原因と本質を特定し、優先順位をつける
- 解決策提示:短期・中期・長期の視点から具体的な施策を提案
例えば、ある製造業の人材育成問題の場合、「OJTが機能していない現状」→「技術伝承システムの欠如という課題」→「メンター制度導入とスキルマップ作成による解決策」といった流れで構築します。
評価されるポイントと差をつける工夫
中小企業診断士の事例問題解答テクニックとして、事例Ⅱでは特に以下の点が評価されます:
| 評価ポイント | 具体的な工夫 |
|---|---|
| 理論的裏付け | マズローの欲求階層説、ハーズバーグの二要因理論などの人事理論を適切に活用 |
| 数値・指標の活用 | 離職率、従業員満足度、労働生産性など具体的指標を用いた分析と目標設定 |
| 実現可能性 | 中小企業の予算・人員制約を考慮した現実的な提案 |
実際の採点データによると、合格者の約75%が理論と実践のバランスに優れた解答を作成しています。また、設問の意図を正確に捉え、与件文から適切に情報を抽出している点も高評価につながっています。
時間配分と解答テクニック
事例Ⅱは配点が高い問題が多いため、時間配分が重要です。全体の120分のうち、読解に20分、構想に15分、解答作成に80分、見直しに5分が理想的です。
解答作成では、PREP法(Point-Reason-Example-Point)を活用すると論理的な文章が書けます。例えば:
「従業員のモチベーション低下が課題です(Point)。なぜなら、評価制度が不明確で公平感がないためです(Reason)。実際、アンケートでは60%の社員が『頑張っても評価されない』と回答しています(Example)。したがって、透明性の高い評価制度の構築が急務です(Point)」

このように、中小企業診断士の事例問題解答テクニックを事例Ⅱに適用することで、採点者に「この診断士なら企業の組織・人事問題を適切に解決できる」と思わせる解答が作成できます。
事例Ⅲ:マーケティング戦略の解答プロセスと差別化のコツ
事例Ⅲの特徴と出題傾向
事例Ⅲは中小企業診断士試験において、マーケティング戦略の理解と応用力を問う重要な科目です。この科目では、商品・サービスの市場投入や販売促進、顧客関係構築などに関する知識が試されます。近年の出題傾向を見ると、従来の4P(Product、Price、Place、Promotion)に加え、顧客体験や顧客価値、デジタルマーケティングの要素が増えています。
特に注目すべきは、単なる知識の暗記ではなく、与えられた状況に対して適切なマーケティング戦略を提案する能力が求められている点です。実務に即した解答が高評価を得るため、理論と実践をバランスよく学ぶことが重要です。
解答構築の3ステップアプローチ
事例Ⅲの解答作成には、以下の3ステップが効果的です:
- 市場環境分析:与えられた情報から市場の特性、競合状況、顧客ニーズを整理します。SWOT分析やPEST分析のフレームワークを活用すると、情報の整理がしやすくなります。
- 課題の特定と優先順位付け:分析結果から、企業が直面している具体的なマーケティング課題を抽出し、重要度と緊急度に基づいて優先順位を付けます。
- 戦略立案と具体的施策の提案:特定した課題に対して、4Pを中心としたマーケティングミックスの観点から具体的な解決策を提案します。
このプロセスを踏むことで、論理的かつ実践的な解答を構築できます。重要なのは、各ステップの関連性を明確にし、一貫した解答を作成することです。
差別化を図るための実践テクニック
中小企業診断士の事例問題解答テクニックとして、他の受験生との差別化を図るポイントをご紹介します:
| テクニック | 具体的方法 |
|---|---|
| 数値を活用した具体化 | 「販売促進費を増やす」ではなく「現状比20%増の販売促進費で、SNS広告に重点配分」など、具体的数値を用いた提案をする |
| トレンドの取り込み | D2C(Direct to Consumer)、オムニチャネル戦略、コンテンツマーケティングなど、最新のマーケティング手法を適切に盛り込む |
| 図表の効果的活用 | ポジショニングマップやカスタマージャーニーマップなど、視覚的に戦略を表現する |
実際の試験では、「この企業ならではの」提案を心がけることが重要です。業界や企業の特性を踏まえた解答は、汎用的な解答よりも高評価を得やすくなります。
よくある失敗パターンと対策
事例Ⅲでよく見られる失敗には、「理論偏重で具体性に欠ける」「企業の状況を無視した一般論」「施策間の整合性がない」などがあります。これらを避けるためには、常に「なぜその戦略が適切なのか」「どのように実行するのか」を意識して解答を作成しましょう。
また、試験時間の配分も重要です。事例Ⅲは情報量が多いため、素早く要点を把握する訓練が必要です。過去問を時間を測って解くことで、効率的な解答作成能力を養うことができます。
中小企業診断士の事例問題解答テクニックを磨くことで、試験合格だけでなく、実務での応用力も身につきます。次回は事例Ⅳについて解説します。
事例Ⅳ:財務・会計分析の解答テクニックと計算問題対策
事例Ⅳの特徴と押さえるべきポイント

事例Ⅳは中小企業診断士試験の集大成とも言える問題で、財務・会計分析に関する知識と計算能力が試されます。この科目は他の事例問題と比較して「正解」が明確であるため、確実に得点源にできる可能性を秘めています。
まず理解すべきは、事例Ⅳが大きく2つのパートに分かれていることです。財務分析による企業の現状把握と、それに基づく改善提案です。特に財務分析では、与えられた数値から適切な指標を算出し、その意味を正確に解釈する能力が求められます。
多くの受験生が躓くポイントは、計算ミスと時間配分です。特に試験の最終科目となることが多い事例Ⅳでは、疲労も蓄積し、単純な計算ミスが増える傾向にあります。
効率的な計算テクニックと時間配分
事例Ⅳの解答作成において、計算問題対策は極めて重要です。以下のテクニックを実践することで、効率的に解答を作成できます。
1. 電卓の活用法
– 四則演算だけでなく、メモリー機能を使いこなす
– 中間計算結果をメモリーに保存し、計算の手戻りを防ぐ
– 計算結果は必ずメモしておき、後から確認できるようにする
2. 時間配分の目安
– 問題文読解:15分
– 財務諸表分析・計算:40分
– 解答作成:35分
– 見直し:10分
計算問題では、まず全体の構造を把握してから細部に入ることが重要です。例えば、損益分岐点分析を行う場合、固定費・変動費の区分から始め、計算式の全体像を確認してから数値を代入するようにしましょう。
解答構成のフレームワーク
中小企業診断士の事例Ⅳでは、以下のフレームワークに沿って解答を構成すると高得点につながります。
1. 現状分析:財務指標の計算結果を示し、業界平均や過去との比較を行う
2. 問題点の抽出:分析結果から企業の財務上の課題を明確にする
3. 改善提案:具体的な数値目標を含めた実行可能な提案を行う
特に改善提案では、「収益性」「安全性」「生産性」「成長性」の4つの視点からバランスよく言及することが評価につながります。例えば、「売上高営業利益率が業界平均の5%に対して2%と低いため、変動費率を3%削減することで利益率を改善する」といった具体的な提案が求められます。
実際の試験では、時間内に計算と文章作成の両方をこなす必要があるため、日頃から過去問を活用した時間配分の練習が欠かせません。中小企業診断士の事例問題解答テクニックの中でも、事例Ⅳは継続的な演習が最も成果に直結する科目と言えるでしょう。
ピックアップ記事



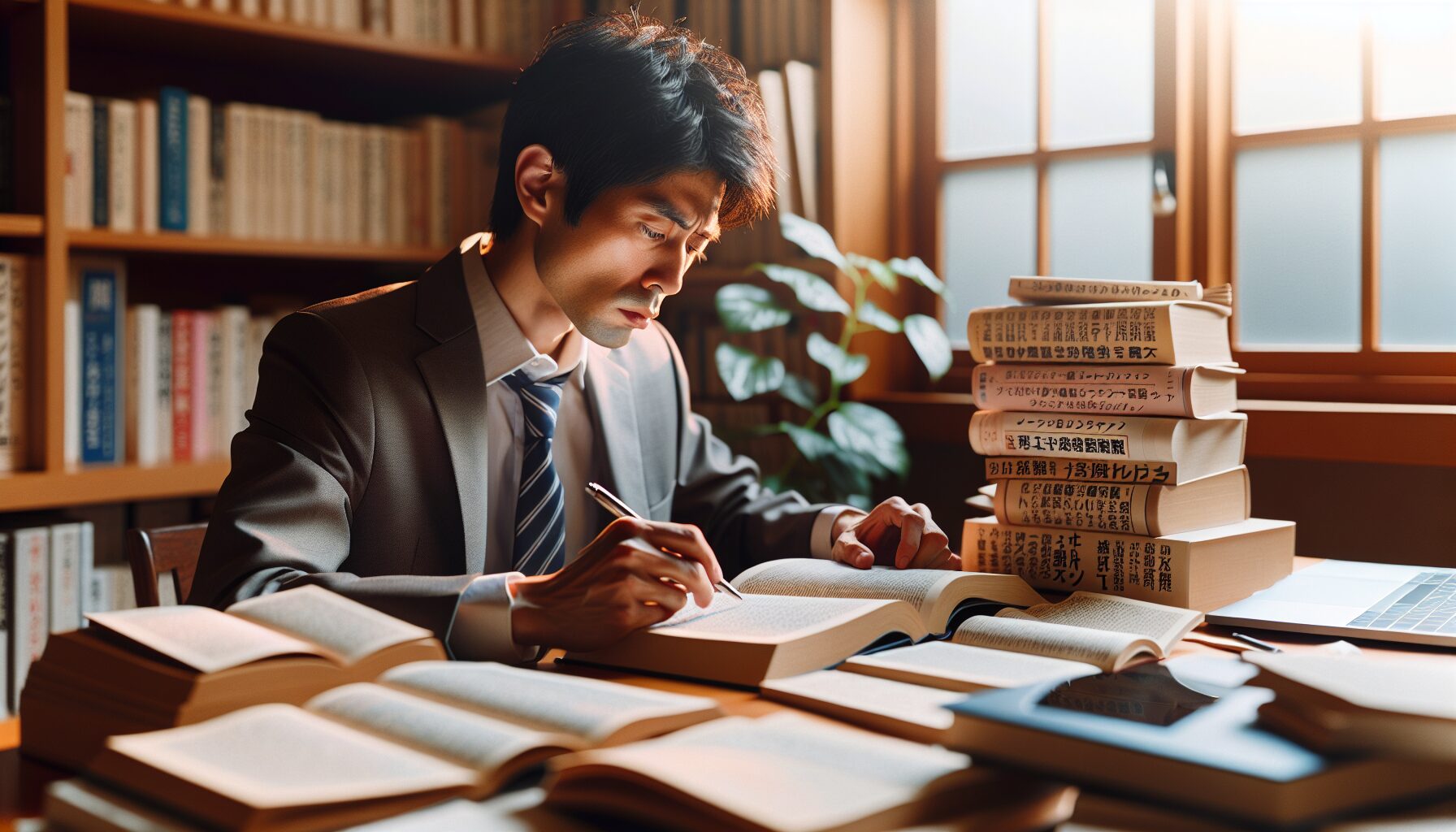
コメント