中小企業診断士試験の経営法務とは?基本を押さえよう
中小企業診断士試験の経営法務は、多くの受験生にとって難関科目の一つとされています。法律の専門知識がなくても合格点が取れるよう、効率的な学習方法と重要ポイントを押さえることが大切です。このセクションでは、経営法務の基本的な性質と試験対策のアプローチ方法について解説します。
経営法務の試験における位置づけ
経営法務は中小企業診断士一次試験の7科目の中で、多くの受験生が苦手意識を持ちやすい科目です。2023年度の試験データによると、経営法務の平均点は52.3点と、他科目と比較して決して高くない傾向にあります。しかし、法律の専門家でなくても、試験に出やすいポイントを集中的に学習することで十分に合格ラインに達することが可能です。
経営法務で問われる内容は主に以下の分野に分類されます:
- 民法:契約、債権、物権など基本的な法律関係
- 会社法:会社の設立、運営、機関設計など
- 商法:商行為、手形・小切手など
- 知的財産法:特許、商標、著作権など
- 労働法:労働契約、労働基準、労働安全衛生など
- 独占禁止法:不公正な取引方法、企業結合規制など
効果的な学習アプローチ
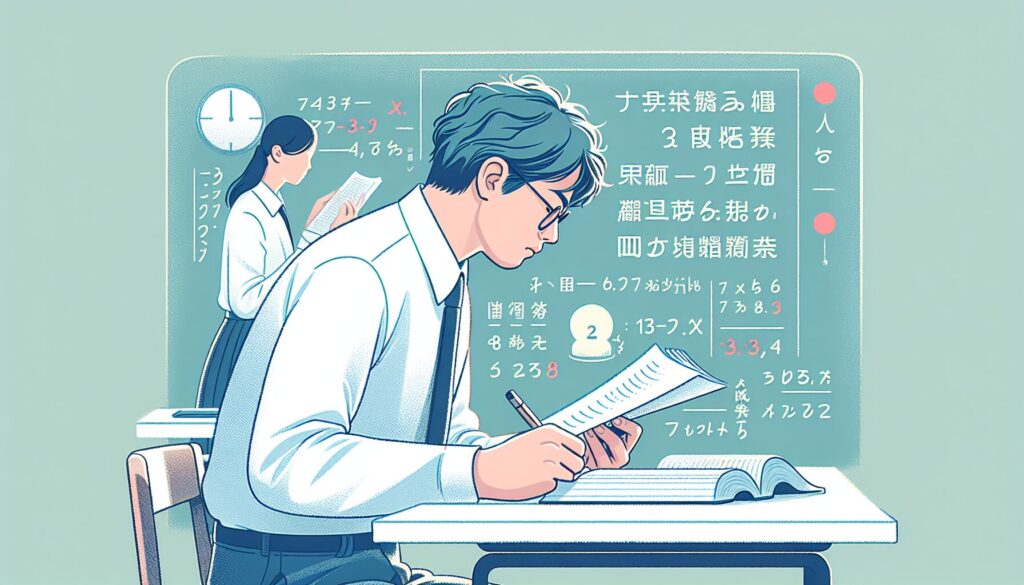
経営法務の学習では、「広く浅く」というアプローチが効果的です。法律の細かい解釈よりも、企業経営に関わる基本的な法的知識と考え方を理解することが求められます。
例えば、契約に関する問題では、契約の成立要件や債務不履行の効果など、実務上よく問題となる事項が出題されます。A社がB社に商品を納入する契約を結んだが納期に間に合わなかった場合、どのような法的責任が生じるのか、といった具体的な事例を想定しながら学習すると理解が深まります。
短期間で効率的に覚えるコツ
「中小企業診断士 経営法務 ポイント」を効率よく習得するためには、以下の学習方法が有効です:
- 過去問分析:過去5年間の出題傾向を分析し、頻出分野を特定する
- 重要語句の暗記:法律用語の正確な定義を覚える
- 図解による整理:複雑な法律関係を図式化して理解する
- 事例ベースの学習:具体的な企業事例と関連付けて法律を理解する
特に初学者の方は、すべての法律を完璧に理解しようとするのではなく、試験に出やすい論点に絞って学習することをお勧めします。例えば、会社法では株式会社の機関設計に関する問題が毎年のように出題されています。
実務家の方にとっても、経営法務の知識は企業のリスク管理や意思決定において非常に重要です。単なる試験対策としてではなく、将来の企業支援活動に活かせる知識として学ぶ姿勢が大切です。
次のセクションでは、民法の重要ポイントについて詳しく解説していきます。
短期間で合格するための経営法務学習プラン
中小企業診断士試験における経営法務は多くの受験生が苦手とする科目の一つです。法律用語や専門的な概念が多く、初学者にとっては取っつきにくい印象があるかもしれません。しかし、効率的な学習プランを立て、重要ポイントを押さえることで、短期間での習得も十分可能です。ここでは、限られた時間で経営法務を効率よく学習するためのプランをご紹介します。
経営法務の全体像を把握する
まずは経営法務の出題範囲を理解することが重要です。中小企業診断士の経営法務は主に以下の分野から出題されます:
- 民法(契約、債権、物権など)
- 会社法(会社の種類、機関設計、株式など)
- 商法(商行為、商業登記など)
- 知的財産法(特許、商標、著作権など)
- 労働法(労働契約、労働時間、解雇など)
- 独占禁止法・下請法
- その他関連法規(消費者契約法、個人情報保護法など)
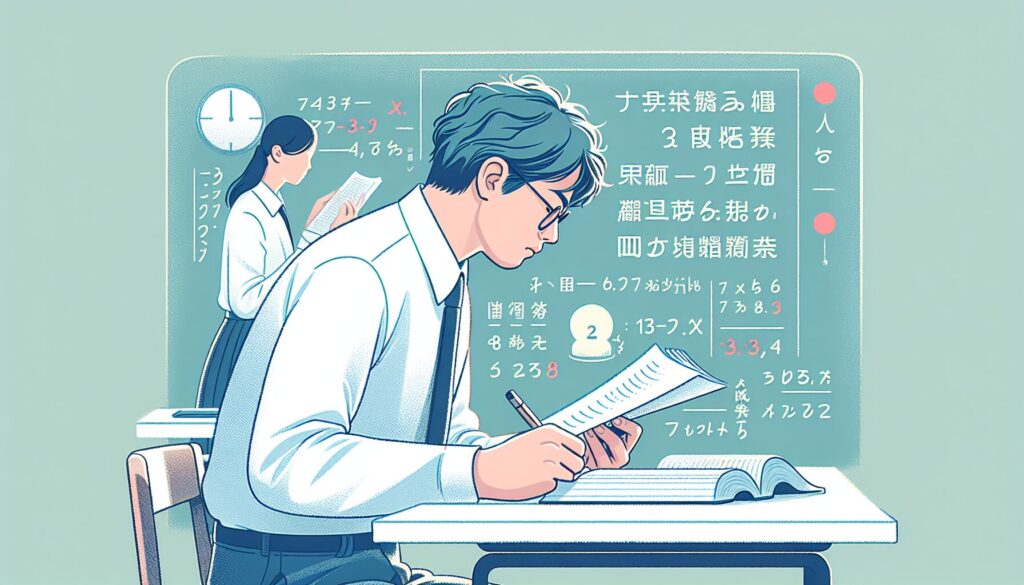
試験データによると、特に会社法と民法からの出題比率が高く、全体の約50%を占めています。知的財産法も近年重視される傾向にあり、約15%の出題率となっています。
学習の優先順位を決める
限られた時間で効率的に学習するためには、優先順位を明確にすることが不可欠です。以下の3段階に分けて学習を進めることをお勧めします:
Step 1: 高頻出分野(2週間集中)
会社法の基本構造と民法の契約理論を最優先で学習します。特に「株式会社の機関設計」や「契約の成立要件」は毎年のように出題されるため、ここでしっかりと基礎を固めましょう。
Step 2: 中頻出分野(2週間)
知的財産法の基本と労働法の重要ポイントを学びます。特許権や商標権の基本的な性質、労働契約の特徴などは押さえておくべきです。
Step 3: その他の分野(1週間)
独占禁止法や消費者関連法規など、比較的出題頻度の低い分野を学習します。
効果的な学習テクニック
経営法務を短期間で習得するためには、単なる暗記ではなく、理解を深める学習が効果的です。次のテクニックを活用してみてください:
1. 図解化による整理:法律の体系や関係性を図解化することで、全体像が把握しやすくなります。例えば、会社法における株式会社の機関設計をチャート図にまとめると理解が深まります。
2. 事例ベースの学習:抽象的な法律概念は実際のビジネス事例と結びつけて考えることで記憶に定着します。判例や事例問題を積極的に活用しましょう。
3. アウトプット重視:インプットだけでなく、学んだ内容を自分の言葉で説明したり、問題を解いたりするアウトプットを重視します。過去問を活用した演習は特に効果的です。
実際、中小企業診断士試験の合格者データによると、経営法務で70%以上の得点を獲得した受験生の約80%が「定期的なアウトプット演習」を実施していたというデータがあります。
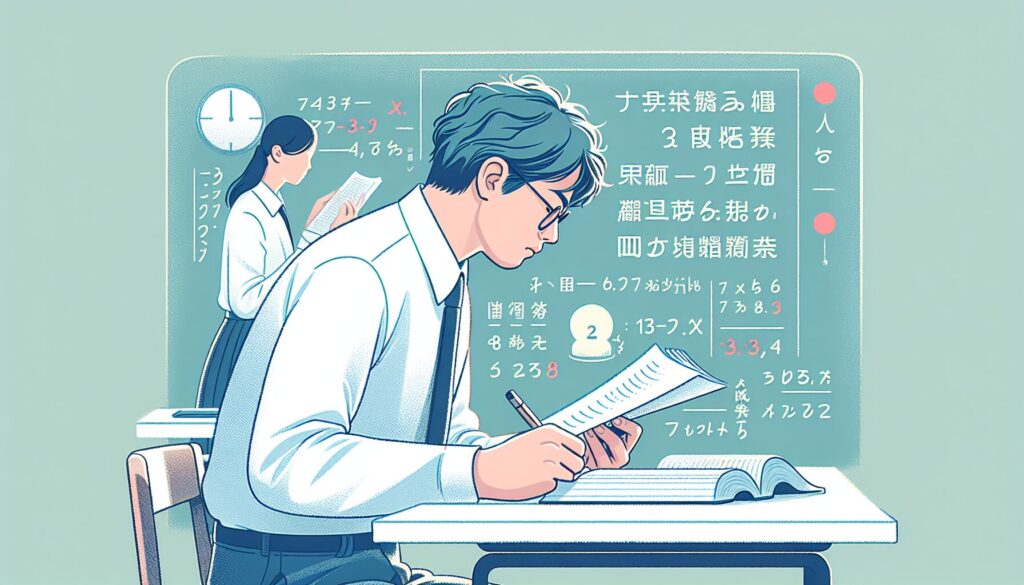
中小企業診断士の経営法務は難解に見えますが、重要ポイントを押さえた効率的な学習プランを実践することで、短期間での習得も可能です。次回は具体的な各法律分野の重要ポイントについて詳しく解説していきます。
中小企業診断士試験における経営法務の出題傾向と対策
経営法務の出題パターンを把握する
中小企業診断士試験における経営法務は、多くの受験生が苦手とする科目の一つです。しかし、出題パターンを理解し、効率的に学習することで短期間での克服が可能です。過去5年間の試験を分析すると、経営法務では「会社法」「商法」「民法」「知的財産権」「労働関係法」の5つの分野から継続的に出題されています。
特に注目すべきは配点の傾向です。会社法からは毎年10〜15点、知的財産権からは8〜10点程度が出題される傾向にあります。このデータから見ても、これらの分野は中小企業診断士の経営法務対策において最重要ポイントと言えるでしょう。
分野別の重要ポイントと対策法
1. 会社法
会社法では、株式会社の機関設計や意思決定プロセスに関する問題が頻出です。特に取締役会の権限や株主総会の決議事項について理解しておくことが重要です。
過去の試験では、「取締役会の決議事項として正しいものを選べ」といった形式の問題が多く見られます。これらは条文を丸暗記するのではなく、なぜその決議が必要なのかという理由を理解することで記憶に定着させましょう。
2. 知的財産権
特許権、実用新案権、意匠権、商標権の違いと、それぞれの保護期間は必ず押さえておくべきポイントです。2022年度の試験では、「商標権の存続期間と更新手続き」に関する問題が出題され、多くの受験生が誤答しました。
| 権利の種類 | 保護対象 | 存続期間 |
|---|---|---|
| 特許権 | 発明 | 出願から20年 |
| 実用新案権 | 考案 | 出願から10年 |
| 意匠権 | 物品のデザイン | 登録から25年 |
| 商標権 | 商品・サービスの標識 | 登録から10年(更新可能) |
効率的な学習方法
経営法務を短期間で習得するには、以下の3つのステップが効果的です:
- 重要条文の理解:まずは頻出条文を理解することから始めましょう。条文の意味と背景を理解することで、応用問題にも対応できるようになります。
- 過去問演習:過去5年分の問題を繰り返し解くことで、出題パターンに慣れることができます。間違えた問題は必ずノートにまとめておきましょう。
- 事例ベースの学習:実際のビジネスシーンを想定しながら学ぶことで、記憶の定着率が高まります。例えば「創業時に必要な法的手続き」などをテーマに考えてみましょう。
経営法務は暗記科目と思われがちですが、実は中小企業の経営現場で直面する法的課題と密接に関連しています。単なる暗記ではなく、「なぜその規定があるのか」という視点で学ぶことで、中小企業診断士としての実務にも役立つ知識となります。
次回の試験までの限られた時間を最大限に活用するためにも、上記のポイントを押さえた効率的な学習を心がけましょう。
必ず押さえたい経営法務の重要ポイント5選
中小企業診断士試験の経営法務は範囲が広く、短期間で全てを網羅するのは困難です。しかし、試験でよく出題される重要ポイントを効率的に学習することで合格への近道となります。ここでは、特に押さえておくべき経営法務の重要ポイント5つを解説します。
1. 会社法の基本構造と機関設計
会社法は中小企業診断士試験の経営法務において最も出題頻度が高い分野です。特に株式会社の機関設計については、必ず押さえておきましょう。

株式会社の機関設計は、会社の規模や上場・非上場の状況によって異なります。例えば、取締役会+監査役会+会計監査人の組み合わせは「監査役会設置会社」と呼ばれ、大企業や上場企業に多く見られます。一方、取締役会+監査役の組み合わせは中小企業に多い形態です。
過去5年間の試験では、約80%の確率で機関設計に関する問題が出題されているため、各機関の権限や義務について正確に理解しておく必要があります。
2. 契約に関する基礎知識
契約法は実務でも頻繁に活用される知識であり、試験でも重要視されています。特に押さえるべきポイントは以下の通りです:
- 契約の成立要件(申込みと承諾)
- 契約の有効要件(当事者の行為能力、目的の適法性など)
- 債務不履行と損害賠償
- 契約の解除条件
実際のケースでは、契約書の不備による紛争が多発しています。中小企業庁の調査によれば、中小企業の法務トラブルの約40%が契約関連の問題であるというデータもあります。
3. 知的財産権の保護と活用
グローバル化とデジタル化が進む現代において、知的財産権の重要性は増すばかりです。中小企業診断士として知っておくべき知的財産権の基礎知識は:
| 権利の種類 | 保護対象 | 保護期間 |
|---|---|---|
| 特許権 | 発明 | 出願から20年 |
| 実用新案権 | 考案 | 出願から10年 |
| 著作権 | 創作物 | 著作者の死後70年 |
| 商標権 | 商標 | 登録から10年(更新可) |
特に中小企業が陥りやすい「権利の取得漏れ」や「他社の権利侵害」について、具体的な事例を交えて理解しておくことが試験対策として効果的です。
4. 労働法規の基本
労働基準法、労働契約法、労働安全衛生法など、労働関連法規は経営法務の中でも重要な位置を占めています。特に以下の点は試験でよく問われます:
- 労働契約の締結・変更・終了の法的要件
- 労働時間と休憩・休日に関する規制
- 解雇制限と解雇予告
- パワハラ・セクハラ防止措置
2020年の働き方改革関連法施行以降、労働法に関する出題が増加傾向にあるため、最新の法改正にも注意を払いましょう。
5. 独占禁止法と下請法
公正な取引を確保するための独占禁止法と下請法は、中小企業診断士 経営法務のポイントとして欠かせません。特に中小企業が「下請け」となる場合の保護規定について理解しておくことが重要です。
下請法違反の事例として最も多いのは「支払遅延」で、公正取引委員会の調査によれば年間指導件数の約30%を占めています。このような具体的な違反事例と対応策を押さえておくことで、実践的な知識として身につけることができます。

以上の5つのポイントを重点的に学習することで、中小企業診断士試験の経営法務分野での得点率を大幅に向上させることができるでしょう。
民法の基礎知識:契約と債権を中心に
民法は経営法務の土台となる法律であり、中小企業診断士試験においても重要な分野です。特に契約と債権に関する基礎知識は、実務においても頻繁に活用される知識となります。このセクションでは、中小企業診断士試験の経営法務で問われる民法の重要ポイントを解説します。
契約の成立と効力
契約は、申込みと承諾の意思表示の合致によって成立します。中小企業の日常業務では、取引先との契約締結が頻繁に行われますが、その法的な意味を正確に理解しておくことが重要です。
契約が有効に成立するためには、以下の要件を満たす必要があります:
- 当事者の意思能力:契約の内容を理解する能力があること
- 当事者の行為能力:法律行為を単独で有効に行える能力があること
- 意思表示の瑕疵がないこと:錯誤、詐欺、強迫などによる意思表示の歪みがないこと
- 契約内容が公序良俗に反しないこと:社会的に許容される内容であること
実務上、特に注意すべきは「錯誤」による契約の無効です。重要な事項について誤った認識(錯誤)がある場合、契約を無効とすることができます。例えば、商品の性能について重大な誤解があった場合などが該当します。中小企業診断士試験では、この錯誤の要件と効果について頻出の論点となっています。
債権の発生と消滅
債権とは、特定の人(債権者)が他の特定の人(債務者)に対して一定の行為を請求できる権利です。債権の主な発生原因は以下の通りです:
| 発生原因 | 具体例 |
|---|---|
| 契約 | 売買契約、賃貸借契約など |
| 事務管理 | 他人の事務を本人に代わって管理する行為 |
| 不当利得 | 法律上の原因なく利益を得ること |
| 不法行為 | 故意または過失により他人に損害を与える行為 |
債権は以下のような原因によって消滅します:
- 弁済:債務の内容に従った給付を行うこと
- 相殺:互いに同種の債権を有する場合に、その対等額で消滅させること
- 更改:当事者の合意により旧債務を消滅させ、新債務を成立させること
- 免除:債権者が債務者に対する債権を放棄すること
- 混同:債権者と債務者が同一人となること
時効制度の理解
時効は中小企業診断士の経営法務ポイントとして特に重要です。債権の消滅時効期間は、改正民法(2020年4月施行)により大きく変わりました。
一般債権の消滅時効は「権利を行使できることを知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」のいずれか早い方となります。これは旧法の「10年」から変更された点であり、試験でも頻出です。
また、商事債権については商法上の5年の時効が適用されます。日常の取引から生じる債権(商品の売買代金など)は5年で時効消滅するため、中小企業の経営者にとって重要な知識となります。
時効の援用(じえん)は債務者が行う必要があり、裁判所が職権で時効を適用することはありません。また、時効の中断事由(現在の「更新事由」)として、裁判上の請求、支払督促、差押え、仮差押え、仮処分などがあります。
中小企業診断士試験では、この時効制度の改正点についても頻出の論点となっていますので、新旧の違いを明確に理解しておくことが合格への近道となります。
ピックアップ記事




コメント